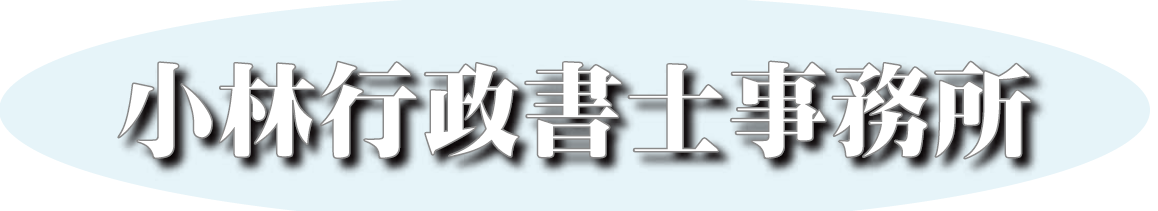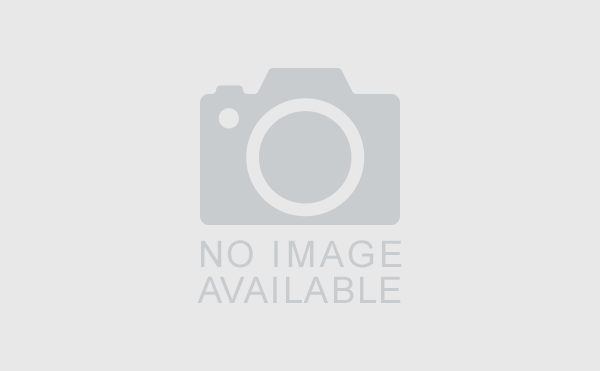一般貨物自動車運送事業への新規参入を満たす基準についてのまとめ <全ト協ハンドブックより>
一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。事業を営むための許可ですから、トラック運送事業者として満たすべき必要な基準が設けられています。
許可の基準は、①申請する者の事業計画が輸送の安全確保のために適切であること、②事業の継続的な遂行のために適切な計画を有していること、③さらにその者が事業を継続して遂行できる能力のあることとなっています。
つまり、トラック運送事業者として新規参入するためには、このような一定の基準を満たす必要があるわけで、これらの基準の詳細については通達において定められています。
この基準となる項目は、次に示すようなものです。① 営業所 ② 車両数 ③ 事業用自動車④ 車庫 ⑤ 休憩・睡眠施設 ⑥ 運行管理体制⑦ 点検及び整備管理体制 ⑧ 資金計画 ⑨ 法令遵守⑩ 損害賠償能力 ⑪ 欠格事由新規参入する者は、この項目にそった事業計画を立て、国土交通大臣に申請を行い、許可を得ることが必要となります。また、この事業計画を変更するときにも、国土交通大臣に事業計画の申請変更を行い、認可などの手続を行うことが必要です。勝手に新規参入時の事業計画を変更することは許されません。
① 営業所
営業所とは、事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。営業所の基準は、次のようなものです。
●使用権原を有すること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するもの
とみなされます。ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り、使用権原を有するものとみなされます。その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示の必要はありません。
●都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められます。その他の関係書類については、添付又は提示の必要はありません。
●規模が適切なものであること。
●必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもって、営業所として適切なものであるかどうか確認されます。申請時に当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真を提出しなければなりません。
② 車両数
事業許可を得るためには、最低車両台数5台を備える必要があります。
● 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5台以上であること。営業所間で共同で使用する事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外には算入されません。
● 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること。けん引車、被けん引車の保有比率については、最低車両台数基準を上回る部分は制限されません。
● 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、5両に満たない場合の特例が設けられていること。
③ 事業用自動車
●計画車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切であること。
●使用権原を有すること。
リース車両については、契約期間がおおむね1年以上で、リース契約の契約書の添付または提示によって使用権原が認められます。
④ 車庫
(改正事業法により、事業用自動車が適切に収容することができることがわかる写真の提出【令和元年11月施行】)
トラックを保有する以上、車庫を保有しなければならないことはいうまでもありません。車庫については、次のような基準が設定されています。
●原則として、営業所に併設すること。ただし、地域によっては営業所に併設できない場合について、平成3年6月25日運輸省告示第340号により例外が認められる場合があります。
● 車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両のすべてを容易に収容できること。
共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱われます。
●他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
令和元年11月の改正事業法の施行により、事業用自動車を適切に収容することが確認できる写真の添付が必要になりました。また、申
請時に車庫として整備が完了していない等、特段の事情がある場合は、事後的に、事業用自動車を適切に収容することが確認できる写真を提出することが必要になりました。
●使用権原を有するものであること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するもの
とみなされます。ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなされます。その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示の必要はありません。
●都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められます。その他の関係書類については、添付又は提示の必要はありません。
● 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
⑤ 休憩・睡眠施設
(改正事業法により、休憩施設に必要な備品等が備え付けられていることがわかる写真の提出【令和元年11月施行】)
トラックの安全運行の確保のためには、ドライバーのための適切な休憩・睡眠施設を備えることが必要になります。この基準は、次のようなものです。
● 原則として、営業所または車庫に併設されること。
● 乗務員が常時有効に利用できる適切な施設で、睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者l人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。令和元年11月の改正事業法の施行により、休憩施設に必要な備品が備えられていることが確認できる写真の添付が必要です。申請時に当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真を提出しなければなりません。
● 使用する権原を有するものであること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものと
みなされます。ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限ります。その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示の必要はありません。
● 都市計画法など関係法令の規定に抵触しないこと。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付が求められます。その他の関係書類については、添付又は提示の必要はありません。
⑥ 運行管理体制
トラック運送事業における安全性の確保等適切な運営を基礎づけるために、事業者の運行管理体制について、次のような基準が定められています。
● 車両数およびその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保すること。
この場合、運転者は日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者または試用期間の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者は除く)であってはなりません。
● 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
● 運転者の勤務時間および乗務時間を定める場合の基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準告示」(平成13年国土交通省告示第1365号)に従うこと。
連続運行はフェリーに乗船する場合を除いて、144時間(6日間)を超えてはなりません。
● 運行管理の担当役員など、運行管理に関する社内の指揮命令系統が明確であること。
● 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
● 事故防止についての教育、指導体制を整え、かつ、事故の処理および自動車事故報告規則に基づく報告の体制が整備されていること。
● 積載危険物等の輸送を行う場合には、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
⑦ 点検及び整備管理体制
(改正事業法により、点検及び整備体制を記載した書類の提出【令和元年11月施行】)
トラックの安全運行を確保するため、事業用自動車の点検及び整備管理体制について、次のような基準が定められています。
● 選任を義務づけられた員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立していること。グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整216号)5-3②に規定される要件を満たす計画でなければなりません。
● 点検及び整備の担当役員など、点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。
整備管理者が選任されていない営業所については、事業者が整備管理を確実に行わなければなりません。
⑧ 資金計画
(改正事業法により、その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有することを明確化【令和元年11月施行】)
トラック運送事業を始めるには、はっきりとした資金計画を立てることが必要です。このため、許可基準において資金計画については以下の基準が設けられています。
●所要資金の見積りが適切なものであること。
● 所要資金の調達に十分な裏づけがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であることなど、資金計画が適切であること。
自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができます。
預貯金額は、申請日時時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の(提示又は)写しの提出により確認されます。
預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認されます。
その他、貨物自動車運送事業法施行規則第3条6号から第8号に規定する添付書類を基本に審査されます。
第6号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
第7号 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項
及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
第8号 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
●自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
⑨ 法令遵守
(改正事業法により、申請者や法人の役員(常勤を問わない)が貨物自動車運送事業法等の違反をした場合、申請日の起算日が前3ヶ月から6 ヶ月(悪質な場合は6 ヶ月から1年)に延長【令和元年11月施行】)
トラック運送事業を営む際には、第一に関係法令の遵守が求められます。したがって、一般貨物運送事業を申請する者あるいは法人の役員は、トラック運送事業の遂行に必要な法令の知識を持っている(法令試験に合格する)ことが必要になります。
法令の遵守状況はさまざまな観点からチェックされますが、健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険及び労働保険の加入義務者がこれら保険に加入していなければなりません。
また、許可などの申請に当たっては申請者またはその法人の業務を執行する役員(名称を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます。また、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者を含みます。)が、貨物自動車運送事業法および道路運送法違反により車両の使用停止(禁止)以上の処分を受けた場合には、その処分期間終了後6 ヵ月(悪質な違反については1年間)以上経過していることが必要とされています。
ここで「悪質な違反」というのは、ア)違反事実もしくはこれを証するものを隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合、イ)飲酒運転、ひき逃げなどの悪質な違反または社会的に影響のある事故を引き起こした場合、ウ)事業の停止処分を受けた場合、です。
また、新規の許可事業者には許可書の交付時に指導講習が行われますが、これには地方適正化実施機関も参画することになっています。指導講習の未受講者には、監査方針に基づいて厳正な対処がなされます。
さらに、新規事業者には事業開始の届出後、1 ヶ月以降3 ヵ月以内に地方適正化実施機関の指導員による巡回指導が実施されることになっています。この巡回指導は営業所、車庫、車両などの現況確認とともに、関係法令の遵守状況が中心に行われます。
⑩ 損害賠償能力
(改正事業法により、対人は1名あたり無制限、対物は1事故あたり200万円以上の任意保険等に加入【令和元年11月施行】)
トラック運送事業を営んでいくうえで、交通事故をはじめいろいろな事故の発生する可能性が常につきまといます。そこでトラック運送事業者は、自らの社会的責任として事故に対する損害賠償能力を備えておくことが必要となります。許可基準においては、次のように定められています。
● 自動車損害賠償保障責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画を有しているほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結など、十分な賠償能力を有すること。
● 特にトラックの保有台数が100両以下の貨物自動車運送事業者は、任意保険などへ加入すること。原則として、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であること。財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上であること。
● 危険物(石油類、化成品類、高圧ガス類など)の輸送に使用する事業用自動車については、上記の他、その輸送に対応する適切な保険へ加入する計画を立て、十分な損害賠償能力を有していること。
● 危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があること。
⑪ 欠格事由
(改正事業法により、欠格期間が2年から5年に延長【令和元年11月施行】)
貨物自動車運送事業の許可を申請する者が、以下の欠格事由に該当する場合などは、許可を受けることができません。
● 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
● 一般貨物運送事業又は特定貨物運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。
令和元年11月の改正事業法の施行により、貨物自動車運送事業の事業許可の取消を受けた者について、再度許可を得ることができない期間(欠格期間)は、5年間と従来よりも延長されました。また、あわせて、処分逃れを目的として廃業を行った場合や、許可取消を受けた者の密接関係者(議決権の過半数を所有する、資本金の1/2を出資している、事業方針の決定について支配力を有している等)についても5年以内に事業許可を得ることができなくなっています。